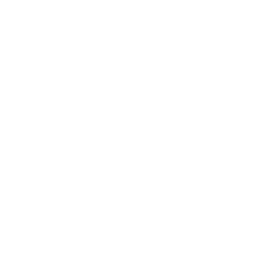目次
離婚した場合の相続権について
離婚をした場合、その前妻との間に子がいる場合には、相続権の有無について問題となることがあります。前妻としては、元夫とともにその資産の形成に寄与したとの思いが強く、相続権を主張してくる場合があります。また、一方で、前妻との間の子は夫にとっても実子であり相続権が存在します。以降、説明していきます。
前妻は相続人になる?_前妻の心理的に納得できない事実
前妻は相続人になるかどうかについては、原則「ならない」とうのが結論です。原則というのは、非常に例外的な例として、生活保護の受給を受ける目的で、形式上離婚したら夫が死亡したような場合、他に子がなく相続人が存在しない場合には、特別受益者としての権利を主張できる場合があります。しかし、いずれにせよ、特別受益者は相続人ではありませんので、元妻は相続人ではないという結論になります。
その根拠は、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」(民法890参照)と規定があることによります。配偶者の定義は婚姻関係にある男女ですので、婚姻関係を解消した元妻はこれにはあたりません。
前妻の子は相続人となるか
「前妻との間に生まれた子」については、婚姻が解消されてもその相続権は喪失しません。
なぜなら「被相続人の子は、相続人となる。」(民法887条)に規定があるからです。被相続人の子は、元妻との間に生まれた子も含みます。
ところで、前妻との子が、「前妻の連れ子」であった場合は事情が異なります。前妻の連れ子は前妻の子でありますが、元夫の子ではありません。ややこしいですが、世間一般的には、親子となりますが、法律上は養子縁組を行わない限り、親子となりません。
そのため、もし前妻との子が「前妻の連れ子」であった場合は、その子の相続権は否定されることとなります。
よくあるトラブル_前妻の子との遺産分割協議
よくあるトラブルとして、前妻の子が、自分の子であり未成年者である場合に生じる場合があります。当然に、まだ父が生きている間は、元夫側では相続が発生しないので問題となることはありません。
一方で、父(元夫)が死亡し相続が発生した場合、他の妻との子がいる場合に、遺産分割協議が難航する場合があります。特にその未成年者が年少であった場合、養育費が必要な関係上、問題が起きやすくなります。
遺言書で相続紛争対策
前述のようなトラブルを防止する方策として、遺言書を作成しておくという対策があります。遺言書には、普通方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。なお、日本法では共同遺言はできませんので、それぞれ各人が、それぞれの遺言を作成する必要があります(民法975条)。
もっとも、お手軽なのが、自筆諸所遺言です。この方式は、前文について自書の必要があり、加除訂正は方式に従って行う必要があります。また、明確な日付の記載が必要で、例えば、「平成30年2月吉日」と記載した場合は無効となります。さらには、末尾に記名と押印が必要となります。この記名は、芸名や通称でも有効ですが、あとで相続人が困るので、本名を記載することをお勧めします。最後に封筒に入れて封印をします。
公正証書遺言とは、公証人に遺言内容について口述し、その内容について公証人が文章に書き起こし、読み聞かせて内容に誤りがないか確認をして、その遺言を作成するというものです。遺言方式の中で、最も信頼性の高い遺言といえますので、遺言書を作成の場合にはこちらをお勧めします。また、後年現実に相続が発生した場合でも、検認と呼ばれる手続きは不要ですので、迅速に相続手続きができる点についても有利です。
秘密証書遺言とは遺言者があらかじめ作成しておいた遺言につき、公証人によって公証してもらう方式です。
遺言書の重要性
遺言書を作成することにより、前妻がいた場合の相続に関する諸問題に対応することができることを既に説明してきました。前妻がいるか否かにかかわらず、遺言書を作成しておくことは、将来の紛争を予防するためにできる確実な方法の1つです。
遺言書を作成しておくことは、被相続人の最後の意思を明らかにすることになります。また相続人の中に、行方不明となった者がいる場合や、意思能力を失った者がいた場合であっても、相続手続を進めることができます。
大げさにいうと、遺言書を作成することは、残された家族のための最高のギフトの1つだといえます。
遺留分についての注意_兄弟姉妹以外の相続人について
まず遺留分の目的は、相続制度が遺族の生活保障及び潜在的持分の精算という考えのもと、相続人のこうした期待権を一定程度保護する目的があると一般に考えられています(内田貴『民法Ⅳ』第5版、東京大学出版会 参照)。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産に対し確保されている一定割合の持分のことをいいます。この遺留分は、各相続人の潜在的な持分の具体化と、遺族の生活保障という側面があるため、この遺留分を侵害するような財産処分行為をキャンセルする強力な効力があります(遺留分減殺請求権:民法1031条)。
そのため、仮に元夫につき、現在の妻との間に子があり、かつ、元妻との間に子がある場合において、元妻の子を除外するような相続分を遺言で定めた場合には、その子の遺留分の侵害となります。そうすると、この遺言を残した元夫が死亡した際、相続が生じますが、この相続分を侵害された元妻の子は、遺留分減殺請求権を行使し、他の相続人に対し自己の遺留分を戻すように請求することができます。
もう少し細かい知識について説明しますと、遺留分の強力な点は、遺留分減殺請求権は「形成権」と呼ばれるものの1種である点です。遺留分減殺請求権は、相手方のある単独行為であって、1度行使されるとその瞬間に、相手方の有無をいわさず、効力が生じるというものです。前述の遺言書を作成する場合には、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が存在することを認識しつつ、これに注意を払って作成する必要があります。
生前贈与での対策
ここまで見てきたように、前妻と前妻との間に子がいる場合において生じる問題について説明してきました。
ところで、こうした問題の解決方法として、生前贈与で解決せよと誘導するものがあるようです。しかしこの話は、相続税の問題と話の中身を取り違えているように考えられます。
確かに、相続税における生前贈与の持ち戻しは3年以内の贈与がその対象となります。
そうすると、例えば死亡する10年前に行われた贈与については、持ち戻しの対象とならず、一般的にいうと、「税務上その贈与がなかったことにはならない」ということになります。
しかし、これはあくまで税務上の話です。民法上の話とは異なります。
民法上は「特別受益」という概念があります。簡単にいうと、相続人のうち、贈与や遺贈を受けたのもがある場合には、そのもの受けた利益を相続時の財産に加算するということです。もっと簡単に結論だけいうと、相続人が受けた生前贈与は無限定に相続財産に加算されるということです。つまり、相続税対策としては有効な手段であっても、遺留分対策としては何ら意味がないということです。
よく税務上の問題と民法上など実体法の問題において、まるで矛盾するかのような、または異なる見解となる場合があります。しかし、これは矛盾していることをいっているわけではなく、民法を例にあげると、これは私人の実体的な権利義務関係について規定している法律です。一方で、各種税法法規は、私人の行為や経済活動によって、実際上に乗じる利益に対し、その課税について規定している法律です。ようするに、同じ現象であっても、権利面から捉えるのと、課税面で捉えるのとでは見え方が違うということです。
まとめ
前妻と前妻の子がいる場合に問題が生じる場合がありますが、その多くは感情的な問題です。特に前妻は、元夫に対し請求できるのは、離婚時の財産分与のみです。相続制度は残された遺族のためにそのルールを決めたものです。離婚した元妻は、最早保護すべき遺族ではないため、基本的にはなにも請求することはできません。
一方で、元妻との間に子が生まれている場合、この子に関しては、相続権があります。特に子が未成年のうちは、元妻が法定代理人となり得るので問題が生じる場合があります。
遺言を作成すれば、一定程度こうした危険を回避できますが、遺言の方式を誤ると無意味になります。また遺留分を無視して遺言を作成すると、これはこれでまた後々問題となります。
現実的な対策は、方式に則った遺言を作成し、かつ、周囲との人間関係を良好に保つことでしょう。