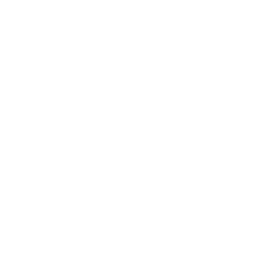目次
寄付する場合は非課税になる_ウワサの真偽について
相続にまつわる種々の遺産の承継方法の1つとして、遺産を国や公共団体等の地方自治体に寄付をして、寄付する財産の課税価格を相続税の対象になる相続財産から切り離すというものがあります。
「寄付する場合は非課税になる」場合があるという事実を、一般の方は「相続税が非課税になる」等と曲解して理解される方が多いようです。
このウワサの真偽とは、寄付行為をしたからといって、必ずしも相続税の全額について非課税となるわけではないということです。また、そもそも、この「寄付」が租税特別措置法上の「国等に対して相続財産を贈与した場合等」に該当しない場合には、相続税の課税価格から寄付に関する財産の価格を引くことはできません(租税特別措置法70条参照)。
残された家族にとって、死亡した被相続人の財産の承継方法については、なんとも悩ましい問題です。昨今は、相続税の非課税枠が小さくなったことで、これまで対象とはならなかた一般の方についても、相続税について注意が必要となりました。
これまでも「寄付」そのものは従来から行われてきました。
元々はその土地の有志が地域の振興を願い、市や町に財産を寄付するなどとして行われてきました。ところが、近年の相続を取り巻く状況の変化が、一般の方にも寄付をすることを考えさせるようになってきています。
遺産を寄付するには
遺産を寄付するためには、相続税の申告期間内に租税特別措置法上の特例を受ける旨の記載をして申告する必要があります。また、寄付をする前提として、寄付にかかる財産の権利関係を整えておく必要があります。
遺贈で寄付する場合_遺言書に記載のある場合
遺産を寄付する場合のやり方として、被相続人の遺志による場合と、相続人の意思による場合があります。ここでは、被相続人の遺志による場合を説明します。
遺贈によって、寄付を行う場合には、前提として被相続人が「遺言書」を作成している必要があります。遺贈とは、被相続人が遺言書を通じて行う単独行為であって、死亡することによりその効力が生じます。また遺贈の執行は、遺言執行者がいる場合にはこの者が行い、不在の場合は、相続人全員でその執行の義務を負担します。
また、遺言書のある場合において、具体的な財産を寄付して欲しいというものではなく、「財産の半分を寄付して欲しい」や、「換価の上その売却益を寄付して欲しい」というのも有効です。しかしながら、手続きが相当に面倒になるので、遺言書を作成する場合には、出来る限り具体的に記載する方が望ましいでしょう。
なお、寄付(遺贈)を受ける国等公共団体は、受遺者としていつでも遺贈を放棄することができます。この場合、その効果は相続の時にさかのぼります(民法986条参照)。
また、同様に寄付の効果についてさかのぼってなかったことになる規定が租税特別措置法70条に記載があります。こちらについては、後述します。
遺贈とは_死因贈与との違い
遺贈は単独行為の遺言によって行われるものであり、死因贈与は贈与契約の一種で単独行為ではありません。簡単に説明すると、遺贈は勝手に「この財産を寄付します」といえますが、死因贈与の場合は「双方合意の上、契約する」必要があります。要するに、死因贈与とは贈与契約の一種ですので、イメージとしては、財産を贈与する人と、財産を受贈する人の双方が契約書を作成して判子を押すようなものです。国と個人では考慮しづらい寄付の形態です。
相続人が相続財産から寄付する場合
相続人が寄付する場合とは、相続人全員の合意により、相続財産について寄付(贈与)を行うことをいいます。この場合、とくに不動産について寄付を行うためには、前提として、相続登記と呼ばれるものを行う必要があります。その理由は一旦、相続人全員の共有状態になった相続財産を、その後の贈与の意思表示に基づき寄付を行うためです。
手続上の問題としては、相続登記の際に登録免許税が必要となるということです。国等の公共団体に帰属させる場合には、非課税となります(登録免許税法4条1項参照)。
相続人が相続財産から寄付を行うことは、遺産分割協議を行うこととなりますので、相続人の中に行方不明のものや、高齢により意思能力の欠如したものがいた場合には、寄付を行うことができません。
また、あとにも記載しますが、国等公共団体は基本的には、私人から寄付を受け入れる体制はできていません(各自治体ホームページ参照)。インターネットで検索をかけていただければ、ご理解いただけると思いますが、まず、寄付を願い出る担当部署が分からないことが多いです。寄付を受け入れていただくまでにも、長大なやりとりと複雑な手続きが必要となります。寄付を行う際には、このあたりを頭に入れておくと良いでしょう。
非課税特例となる場合
非課税特例に該当するためには、2つのポイントがあります。1つは、寄付の相手先が国等の公共団体であることです。もう1つは、相続税又は贈与税の負担を不当に減少する結果となる目的のないこと(租税特別措置法70条1項参照)です。つまり、恣意的な相続税対策としての寄付ではないことがポイントとなります。
以降詳しく説明していきます。
国等公共団体または公益社団法人若しくは公益財団法人等に寄付する場合
国等公共団体に寄付をする場合には、前述の1つ目の要件については問題とはなりません。ただし、相手のあることなので、国等地方公共団体側から、寄付を拒否される可能性もあります。
また、公益社団法人若しくは公益財団法人等であっても、一般に、すべてのこれら法人等に寄付をした場合に特例が認められるわけではありません。その法人が「教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるもの」(租税特別措置法70条1項後段)でなければなりません。
また、仮にこうした法人に対しての寄付が、一旦は特例に該当する寄付と認められた場合であっても、贈与があった日から2年を経過してもその財産の活用がなかった場合には、特例は適用されなかったということになります(租税特別措置法70条2項)。このことが、前に遺贈の放棄について説明した、効果のさかのぼる類似の規定です。
なお、この場合は、修正申告書の提出が必要となり、四月以内に修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければなりません(租税特別措置法70条6項)。
公益信託の信託財産に支出をする場合
おもに特定公益信託のうち、認定特定公益信託の場合、その信託に拠出し他財産についてはは相続税が課されません。
特定公益信託とは公益信託ニ関スル法律による信託のことです。
租税特別措置法上の特例を受けることができるのは、特定公益信託に基づく信託のうち、「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出」(租税特別措置法70条3項)した場合となります。
この場合も前述の国等公共団体に寄付した場合と同様に、一定の期間内に実質的に利用されなければ、その寄付した財産は、相続財産の価格の内側に戻されることとなります。
特例を受けられない場合
租税特別措置法上の特例を受けられない場合として、専ら節税を図る場合が挙げられます。そのほかにも、対象として除外されてしまう場合がいくつかあります。最後に寄付を行う場合の注意点について、説明します。
制度利用の注意点について
本稿の初めにて既に説明をしましたが、寄付を行うにせよ、認定特定信託を行うにせよ、専ら節税の効果を見込んで行ってはいけません。仮に、節税を主たる目的とした寄付行為であった場合には、一般的には、課税逃れであるとして、指摘を受ける可能性があります。
寄付を行う場合には、寄付の相手先となる機関との協議が必要となります。一般的には、寄付の対象となる財産につき、権利関係で争いのないことが、寄付を受け入れる側の要件の1つです。つまり、遺言がある場合は別として、遺産分割協議が整っている必要がありますし、不動産においては、相続登記を放置していた場合には、遺言者である被相続人の名義になっていることが前提となります。
認定特定信託を行う場合であっても、後に特定公益信託に該当しないこととなった場合には、修正申告が必要となる可能性があります。
認定特定信託を行う場合には、主務大臣の認定を受けたものでなければならないので、実際には事前に信託銀行等の信託業務を専門に扱う信託事業者に相談してみるのも1つの手段です。
上記のいずれを行うにせよ、非常に手続きが複雑になるので、可能であれば前もって、寄付の場合には相手先と連携をとり相談をする必要があります。同様に、認定特定信託を行う場合においても、主務大臣の認定が必要ですので、あらかじめの情報収集が重要です。
まとめ
租税特別措置法上の特例を受けるためには、可能であれば、まず前もって関係機関に相談するのがよいでしょう。一方で、一般に、相続税の申告は、相続を知ったときから4か月以内にしなければなりません。この期間内に手続き進めるためには、事前の段取りがどこまでできているかが重要となります。
寄付や認定特定信託は、そもそも目的が公益のためで、とりわけ学術振興にその中心が置かれています。制度の利用には、未来を担う若者や子供たちのため公益となることをしたいと思う心が大事ではないでしょうか。
理念としては素晴らしい制度ですので、相続税対策や節税といった私的な欲求のためには利用したくないものです。